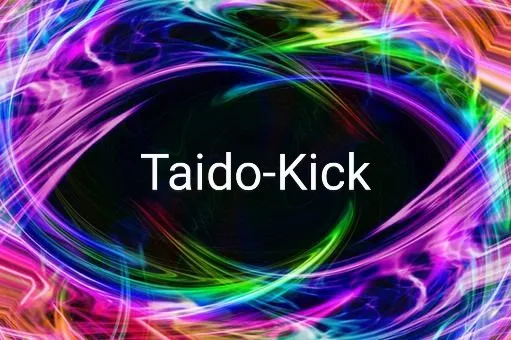HOME > 電磁気学 > マクスウェル方程式 > アンペール-マクスウェルの式
【前ページ】 【次ページ】
本ページでは…
本ページでは、マクスウェル方程式を構成するアンペール-マクスウェルの式
\begin{align*}\boldsymbol\nabla×\boldsymbol H&=\boldsymbol j+\frac{\partial \boldsymbol D}{\partial t}\ \ \ \ \left(\text{rot}\boldsymbol H=\boldsymbol j+\frac{\partial \boldsymbol D}{\partial t}\right)\end{align*}
または
\begin{align*}\int_C\boldsymbol H\cdot d\boldsymbol l&=\int_S \left(\boldsymbol j+\frac{\partial \boldsymbol D}{\partial t}\right)\cdot d\boldsymbol S\end{align*}
を導く。また、アンペール-マクスウェルの式からアンペールの法則が導かれることを確認する。
前ページでは…
前ページでは、マクスウェル方程式を構成するマクスウェル-ガウスの式
\begin{align*}\boldsymbol \nabla\cdot\boldsymbol D&=\rho\ \ \ \ (\text{div}\boldsymbol D=\rho)\end{align*}
または
\begin{align*}\int_S \boldsymbol D\cdot d\boldsymbol S&=Q_\text f\end{align*}
を導いた。また、マクスウェル-ガウスの式から電場\(\boldsymbol E\)の定義や分極\(\boldsymbol P\)の定義、そして、クーロンの法則(静電場)が導かれることを確認した。
内容
アンペール-マクスウェル方程式とは
\begin{align*}\boldsymbol\nabla×\boldsymbol H&=\boldsymbol j+\frac{\partial \boldsymbol D}{\partial t}\ \ \ \ \left(\text{rot}\boldsymbol H=\boldsymbol j+\frac{\partial \boldsymbol D}{\partial t}\right)\tag{1}\end{align*}
または
\begin{align*}\int_C\boldsymbol H\cdot d\boldsymbol l&=\int_S \left(\boldsymbol j+\frac{\partial \boldsymbol D}{\partial t}\right)\cdot d\boldsymbol S\tag{2}\end{align*}
をアンペール-マクスウェルの式という。この式は電流\(\int_S\boldsymbol j\cdot d\boldsymbol S\)または変位電流\(\int_S\frac{\partial\boldsymbol D}{\partial t}\cdot d\boldsymbol S\)の周りにはループしている磁場\(\boldsymbol H\)があることを示し、電流によって磁場\(\boldsymbol H\)が生じることを表したアンペールの法則(以前のページを参照)に変位電流によって生じる磁場を加えたものである。
ここで、変位電流とは電束密度\(\boldsymbol D\)の閉曲面\(S\)における法線成分の面積分が時間的に変位するときに生じる電流であり、電荷の移動で生じる通常の電流とは異なる。変位電流の例としてコンデンサーがあり、コンデンサーに導線を繋ぎ放電させるとき、コンデンサーの電極間に変位電流が生じて閉回路が作られる。また、雷も変位電流の例であり、落雷によって雷雲から放電する際に、落雷とは別に雷雲と地面の間に変位電流が生じて閉回路が作られる。
アンペール-マクスウェルの式の導出
アンペール-マクスウェルの式を導出する。
E-B対応において、磁気力線には湧き出し源は無く、磁気力線は途切れたり、別の磁気力線と交わったりしないものと定義した(以前のページを参照)。ここで、自由電流(磁化電流は含まない)の向きを右ねじが進む向きとしたとき、電流から生じる磁気力線の向きは右ねじが進むときに回る向きとなり、磁気力線の密度である磁場\(\boldsymbol H\)を閉曲線\(C\)上で線積分したとき、その量は閉曲線\(C\)がつくる面\(S\)を貫く自由電流の量\(I_\text f\)になると定義した。
\begin{align*}\int_C\boldsymbol H\cdot d\boldsymbol l&=I_\text f\tag{3}\end{align*}
ここで、自由電流の電流密度\(\boldsymbol j\)を次のように定義
\begin{align*}I_\text f=\int_S\boldsymbol j\cdot d\boldsymbol S\tag{4}\end{align*}
すると、式(3)は
\begin{align*}\int_C\boldsymbol H\cdot d\boldsymbol l&=\int_S \boldsymbol j\cdot d\boldsymbol S\tag{5}\end{align*}
となって、ここに変位電流\(\int_S\frac{\partial\boldsymbol D}{\partial t}\cdot d\boldsymbol S\)の周りにもループしている磁場\(\boldsymbol H\)が存在することを考慮すると
\begin{align*}\int_C\boldsymbol H\cdot d\boldsymbol l&=\int_S \left(\boldsymbol j+\frac{\partial \boldsymbol D}{\partial t}\right)\cdot d\boldsymbol S\tag{2}\end{align*}
となって、アンペール-マクスウェルの式の積分形を求めることができる。
微分形で表したアンペール-マクスウェルの式は次のように求めることができる。閉曲線\(C\)で囲われた面を\(S\)としたとき、ストークスの定理は
\begin{align*}\int_S (\boldsymbol \nabla×\boldsymbol f)\cdot d\boldsymbol S=\int_C \boldsymbol f\cdot d\boldsymbol l\tag{6}\end{align*}
となる(以前のページを参照)ため、積分形で表したアンペール-マクスウェルの式(2)に代入すると
\begin{align*}\int_S (\boldsymbol \nabla×\boldsymbol H)\cdot d\boldsymbol S&=\int_S \left(\boldsymbol j+\frac{\partial \boldsymbol D}{\partial t}\right)\cdot d\boldsymbol S\tag{7}\end{align*}
となる。ここで、アンペール-マクスウェルの式(2)はあらゆる閉曲線\(C\)で成り立つため、式(7)の面積分はあらゆる面\(S\)で成り立たなければならず、次式が成り立つ。
\begin{align*}\boldsymbol\nabla×\boldsymbol H&=\boldsymbol j+\frac{\partial \boldsymbol D}{\partial t}\ \ \ \ \left(\text{rot}\boldsymbol H=\boldsymbol j+\frac{\partial \boldsymbol D}{\partial t}\right)\tag{1}\end{align*}
となる。これが、微分形で表したアンペール-マクスウェルの式である。
アンペール-マクスウェルの式から導かれる式
アンペールの法則
以前のページで求めたが、アンペール-マクスウェルの式とローレンツ力の式からアンペールの法則およびアンペール力を求めることができる。
次ページから…
次ページでは、電磁場中で運動する荷電粒子が受けるローレンツ力
\begin{align*}\boldsymbol F=q\boldsymbol E+q\boldsymbol v×\boldsymbol B\end{align*}
について調べる。
【前ページ】 【次ページ】
HOME > 電磁気学 > マクスウェル方程式 >アンペール-マクスウェルの式