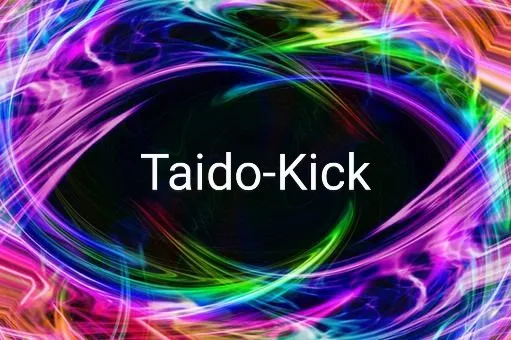HOME > 物理数学 > ベクトル解析 >発散
【前ページ】 【次ページ】
本ページでは…
本ページでは、発散が流束密度であるベクトル場の各点のベクトル値を、大きさが「点を含む微小体積における単位体積あたりの湧き出した流束」であるスカラーに置き換える作用素であることをみる。また、3次元デカルト座標では発散\(\boldsymbol\nabla\cdot\)は
\begin{align*}\boldsymbol\nabla\cdot=\left(\frac{\partial }{\partial x},\frac{\partial }{\partial y},\frac{\partial }{\partial z}\right)\cdot\end{align*}
となることを求める。
前ページまで…
前ページでは、以下の勾配の公式を求めた。
\begin{align*}\boldsymbol\nabla\vert\boldsymbol r\vert^n=n\vert\boldsymbol r\vert^{n-2}\boldsymbol r\end{align*}
\begin{align*}\boldsymbol\nabla(\boldsymbol r\cdot\boldsymbol a)=\boldsymbol a\end{align*}
内容
流束と流束密度
空間にある流れが存在するとき、流れているものの量を流束といい、単位面積あたりの流束を流束密度という。流束密度はベクトル場であり、流束密度であるベクトル場\(\boldsymbol f\)の\(x\),\(y\),\(z\)成分に面積を掛けると、\(x\),\(y\),\(z\)の向きに面積を通過する流速が得られる。
流束の例としては、電束や磁束、電気力線、磁気力線などがあり、それぞれの流束密度は電束密度や磁束密度、電場、磁場である。
発散
流束密度であるベクトル場の各点におけるベクトル値を、大きさが「点を含む微小体積における単位体積あたりの湧き出した流束」である発散スカラーに対応させる作用素(演算子)を発散といい、\(\boldsymbol\nabla\cdot\)または\(\text{div}\)で表す。この発散によって、ベクトル場は発散スカラー場と呼ばれるスカラー場に変換され、ベクトル場を\(\boldsymbol f\)とすると勾配ベクトル場は\(\boldsymbol \nabla\cdot\boldsymbol f\)と表される。つまり、常に発散はベクトル場に作用し、作用後はスカラー場となる。
3次元デカルト座標における発散
3次元デカルト座標における発散が
\begin{align*}\boldsymbol\nabla\cdot=\left(\frac{\partial }{\partial x},\frac{\partial }{\partial y},\frac{\partial }{\partial z}\right)\cdot\tag{1}\end{align*}
となること、言い換えると、ベクトル場が\(\boldsymbol f=(f_x,f_y,f_z)\)のときに発散スカラー\(\boldsymbol\nabla \cdot\boldsymbol f\)
\begin{align*}\boldsymbol \nabla \cdot \boldsymbol f=\frac{\partial f_x}{\partial x}+\frac{\partial f_y}{\partial y}+\frac{\partial f_z}{\partial z}\tag{2}\end{align*}
の大きさが「点を含む微小体積における単位体積あたりの湧き出した流束(値が負であれば、吸い込まれを示す)」であることを確認する。
初めに、ある点\((x,y,z)\)において、点\((x,y,z)\)と点\((x+dx,y+dy,z+dz)\)を含み一辺が\(dx\),\(dy\),\(dz\)である立方体の微小体積を考える。
点\((x,y,z)\)を通り、\(x\)軸に垂直な面\(dy×dz\)から微小体積に入る流速は\(f_xdydz\)となる(流束の値が負であれば、微小体積を出ていることを示す)。一方、点\((x+dx,y+dy,z+dz)\)を通り、\(x\)軸に垂直な面\(dy×dz\)から立方体を出る流速は\(f_{x+dx}dydz\)となる(流束の値が負であれば、微小体積に入っていることを示す)。よって、\(x\)軸方向において、微小体積を出る流束から入る流束を引いた流束、つまり微小体積から湧き出した流束は
\begin{align*}f_{x+dx}dydz-f_xdydz=(f_{x+dx}-f_x)dydz\tag{3}\end{align*}
となる(流速の値が負であれば、微小体積へ吸い込まれていることを示す)。また、次の関係
\begin{align*}f_{x+dx}-f_x&=f_x+\left(\frac{\partial f_x}{\partial x}dx\right)-f_x\\&=\frac{\partial f_x}{\partial x}dx\tag{4}\end{align*}
を用いると式(3)は
\begin{align*}\frac{\partial f_x}{\partial x}dxdydz\tag{5}\end{align*}
となる。
\(y\)軸方向および\(z\)軸方向においても\(x\)軸方向と同様に、微小体積から湧き出した流束は
\begin{align*}\frac{\partial f_y}{\partial y}dxdydz\tag{6}\\\frac{\partial f_z}{\partial z}dxdydz\tag{7}\end{align*}
となる。よって、全方向において微小体積から湧き出した流束は
\begin{align*}\left(\frac{\partial f_x}{\partial x}+\frac{\partial f_y}{\partial y}+\frac{\partial f_z}{\partial z}\right)dxdydz\tag{8}\end{align*}
であり、単位体積あたりの湧き出した流束は微小体積\(dxdydz\)で割った
\begin{align*}\left(\frac{\partial f_x}{\partial x}+\frac{\partial f_y}{\partial y}+\frac{\partial f_z}{\partial z}\right)\tag{9}\end{align*}
となる。これが、発散スカラーである。
3次元球面座標における発散
3次元デカルト座標のときと同様に、3次元球面座標\((r,\theta,\phi)\)において勾配\(\boldsymbol\nabla\)は
\begin{align*}\boldsymbol\nabla&=\left(\frac{\partial }{\partial r},\frac{1}{r}\frac{\partial }{\partial \theta},\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial }{\partial \phi}\right)\\&=\boldsymbol e_r\frac{\partial }{\partial r}+\boldsymbol e_\theta\frac{1}{r}\frac{\partial }{\partial \theta}+\boldsymbol e_\phi\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial }{\partial \phi}\tag{10}\end{align*}
書くことができた。ここで、3次元球面座標における基底ベクトル\(\boldsymbol e_r\),\(\boldsymbol e_\theta\),\(\boldsymbol e_\phi\)を用いてベクトル場を
\begin{align*}\boldsymbol f&=f(f_r,f_\theta,f_\phi)\\&=\boldsymbol e_rf_r+\boldsymbol e_\theta f_\theta+\boldsymbol e_\phi f_\phi\tag{11}\end{align*}
と置くと、発散スカラーは
\begin{align*}\boldsymbol\nabla\cdot\boldsymbol f&=\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2f_r)+\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial }{\partial \theta}(\sin\theta f_\theta)+\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial f_\phi}{\partial \phi}\tag{12}\end{align*}
\begin{align*}\boldsymbol\nabla\cdot\boldsymbol f&=\left(\frac{\partial }{\partial r},\frac{1}{r}\frac{\partial }{\partial \theta},\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial }{\partial \phi}\right)\cdot\boldsymbol f\\&=\left(\boldsymbol e_r\frac{\partial }{\partial r}+\boldsymbol e_\theta\frac{1}{r}\frac{\partial }{\partial \theta}+\boldsymbol e_\phi\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial }{\partial \phi}\right)\cdot(\boldsymbol e_rf_r+\boldsymbol e_\theta f_\theta+\boldsymbol e_\phi f_\phi)\\&=\frac{\partial f_r}{\partial r}+\frac{2f_r}{r}+\frac{1}{r}\frac{\partial f_\theta}{\partial \theta}+\frac{\cos\theta}{r\sin\theta}f_\theta+\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial f_\phi}{\partial \phi}\\&=\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2f_r)+\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial }{\partial \theta}(\sin\theta f_\theta)+\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial f_\phi}{\partial \phi}\end{align*}
3行目への変形では、3次元球面座標における基底ベクトルの偏微分の関係
\begin{align*}\frac{\partial \boldsymbol e_r}{\partial r}&=\boldsymbol 0\\\frac{\partial \boldsymbol e_\theta}{\partial r}&=\boldsymbol 0\\\frac{\partial \boldsymbol e_\phi}{\partial r}&=\boldsymbol 0\\\frac{\partial \boldsymbol e_r}{\partial \theta}&=\boldsymbol e_\theta\\\frac{\partial \boldsymbol e_\theta}{\partial \theta}&=-\boldsymbol e_r\\\frac{\partial \boldsymbol e_\phi}{\partial \theta}&=\boldsymbol 0\\\frac{\partial \boldsymbol e_r}{\partial \phi}&=\sin\theta\boldsymbol e_\phi\\\frac{\partial \boldsymbol e_\theta}{\partial \phi}&=\cos\theta\boldsymbol e_\phi\\\frac{\partial \boldsymbol e_\phi}{\partial \phi}&=-\sin\theta\boldsymbol e_r-\cos\theta\boldsymbol e_\theta\end{align*}
と基底ベクトルの性質
\begin{align*}&\vert\boldsymbol e_r\vert^2=\vert\boldsymbol e_\theta\vert^2=\vert\boldsymbol e_\phi\vert^2=1\\&\boldsymbol e_r\cdot\boldsymbol e_\theta=\boldsymbol e_\theta\cdot\boldsymbol e_\phi=\boldsymbol e_\phi\cdot\boldsymbol e_r=0\end{align*}
を用いた。3次元球面座標における基底ベクトルの偏微分では、位置ベクトル\(\boldsymbol r\)
\begin{align*}\boldsymbol r=\boldsymbol e_xr\sin\theta\cos\phi+\boldsymbol e_yr\sin\theta\sin\phi+\boldsymbol e_zr\cos\theta\end{align*}
を偏微分して求めた3次元球面座標における基底ベクトル
\begin{align*}\boldsymbol e_r&=\frac{\partial \boldsymbol r}{\partial r}/\left\vert\frac{\partial \boldsymbol r}{\partial r}\right\vert\\&=(\boldsymbol e_x\sin\theta\cos\phi+\boldsymbol e_y\sin\theta\sin\phi+\boldsymbol e_z\cos\phi)/1\\&=\boldsymbol e_x\sin\theta\cos\phi+\boldsymbol e_y\sin\theta\sin\phi+\boldsymbol e_z\cos\phi\\\boldsymbol e_\theta&=\frac{\partial \boldsymbol r}{\partial \theta}/\left\vert\frac{\partial \boldsymbol r}{\partial \theta}\right\vert\\&=(\boldsymbol e_xr\cos\theta\cos\phi+\boldsymbol e_yr\cos\theta\sin\phi-\boldsymbol e_zr\sin\phi)/r\\&=\boldsymbol e_x\cos\theta\cos\phi+\boldsymbol e_y\cos\theta\sin\phi-\boldsymbol e_z\sin\phi\\\boldsymbol e_\phi&=\frac{\partial \boldsymbol r}{\partial \phi}/\left\vert\frac{\partial \boldsymbol r}{\partial \phi}\right\vert\\&=(-\boldsymbol e_xr\sin\theta\sin\phi+\boldsymbol e_yr\sin\theta\cos\phi)/r\sin\theta\\&=-\boldsymbol e_x\sin\phi+\boldsymbol e_y\cos\phi\end{align*}
と、3次元デカルト座標における基底ベクトルは単なる定数であり偏微分するとゼロになることを用いた。
となる。
3次元円筒座標における発散
3次元円筒座標\((\rho,\phi,z)\)において勾配\(\boldsymbol\nabla\)は
\begin{align*}\boldsymbol\nabla=\left(\frac{\partial }{\partial \rho},\frac{1}{\rho}\frac{\partial }{\partial \phi},\frac{\partial }{\partial z}\right)\tag{12}\end{align*}
書くことができた。ここで、3次元円筒座標における基底ベクトル\(\boldsymbol e_\rho\),\(\boldsymbol e_\phi\),\(\boldsymbol e_z\)を用いてベクトル場を
\begin{align*}\boldsymbol f&=f(f_\rho,f_\phi,f_z)\\&=\boldsymbol e_\rho f_\rho+\boldsymbol e_\phi f_\phi+\boldsymbol e_z f_z\tag{11}\end{align*}
と置くと、発散スカラーは
\begin{align*}\boldsymbol\nabla\cdot\boldsymbol f=\frac{1}{\rho}\frac{\partial }{\partial \rho}(\rho f_\rho)+\frac{1}{\rho}\frac{\partial f_\phi}{\partial \phi}+\frac{\partial f_z}{\partial z}\tag{13}\end{align*}
となる。
\begin{align*}\boldsymbol\nabla\cdot\boldsymbol f&=\left(\frac{\partial }{\partial \rho},\frac{1}{\rho}\frac{\partial }{\partial \phi},\frac{\partial }{\partial z}\right)\cdot\boldsymbol f\\&=\left(\boldsymbol e_\rho\frac{\partial }{\partial \rho}+\boldsymbol e_\phi\frac{1}{\rho}\frac{\partial }{\partial \phi}+\boldsymbol e_z\frac{\partial }{\partial z}\right)\cdot(\boldsymbol e_\rho f_\rho+\boldsymbol e_\phi f_\phi+\boldsymbol e_z f_z)\\&=\frac{\partial f_\rho}{\partial \rho}+\frac{f_\rho}{\rho}+\frac{1}{\rho}\frac{\partial f_\phi}{\partial \phi}+\frac{\partial f_z}{\partial z}\\&=\frac{1}{\rho}\frac{\partial }{\partial \rho}(\rho f_\rho)+\frac{1}{\rho}\frac{\partial f_\phi}{\partial \phi}+\frac{\partial f_z}{\partial z}\end{align*}
3行目への変形では、3次元円筒座標における基底ベクトルの偏微分の関係
\begin{align*}\frac{\partial \boldsymbol e_\rho}{\partial \rho}&=\boldsymbol 0\\\frac{\partial \boldsymbol e_\phi}{\partial \rho}&=\boldsymbol 0\\\frac{\partial \boldsymbol e_z}{\partial \rho}&=\boldsymbol 0\\\frac{\partial \boldsymbol e_\rho}{\partial \phi}&=\boldsymbol e_\phi\\\frac{\partial \boldsymbol e_\phi}{\partial \phi}&=-\boldsymbol e_\rho\\\frac{\partial \boldsymbol e_z}{\partial \phi}&=\boldsymbol 0\\\frac{\partial \boldsymbol e_\rho}{\partial z}&=\boldsymbol 0\\\frac{\partial \boldsymbol e_\phi}{\partial z}&=\boldsymbol 0\\\frac{\partial \boldsymbol e_z}{\partial z}&=\boldsymbol 0\end{align*}
と基底ベクトルの性質
\begin{align*}&\vert\boldsymbol e_\rho\vert^2=\vert\boldsymbol e_\phi\vert^2=\vert\boldsymbol e_z\vert^2=1\\&\boldsymbol e_\rho\cdot\boldsymbol e_\phi=\boldsymbol e_\phi\cdot\boldsymbol e_z=\boldsymbol e_z\cdot\boldsymbol e_\rho=0\end{align*}
を用いた。3次元円筒座標における基底ベクトルの偏微分では、位置ベクトル\(\boldsymbol \rho\)
\begin{align*}\boldsymbol \rho=\boldsymbol e_x\rho\cos\phi+\boldsymbol e_y\rho\sin\phi+\boldsymbol e_zz\end{align*}
を偏微分して求めた3次元円筒座標における基底ベクトル
\begin{align*}\boldsymbol e_\rho&=\frac{\partial \boldsymbol \rho}{\partial \rho}/\left\vert\frac{\partial \boldsymbol \rho}{\partial \rho}\right\vert\\&=(\boldsymbol e_x\cos\phi+\boldsymbol e_y\sin\phi)/1\\&=\boldsymbol e_x\cos\phi+\boldsymbol e_y\sin\phi\\\boldsymbol e_\phi&=\frac{\partial \boldsymbol \rho}{\partial \phi}/\left\vert\frac{\partial \boldsymbol \rho}{\partial \phi}\right\vert\\&=(-\boldsymbol e_x\rho\sin\phi+\boldsymbol e_y\rho\cos\phi)/\rho\\&=-\boldsymbol e_x\sin\phi+\boldsymbol e_y\cos\phi\\\boldsymbol e_z&=\frac{\partial \boldsymbol \rho}{\partial z}/\left\vert\frac{\partial \boldsymbol \rho}{\partial z}\right\vert\\&=\boldsymbol e_z\end{align*}
と、3次元デカルト座標における基底ベクトルは単なる定数であり偏微分するとゼロになることを用いた。
次ページから…
次ページでは、以下の発散の公式を求める。
\begin{align*}\boldsymbol \nabla\cdot(\boldsymbol\nabla×\boldsymbol f)=0\end{align*}
\begin{align*}\boldsymbol\nabla\cdot\boldsymbol r&=3\end{align*}
\begin{align*}\boldsymbol\nabla\cdot(\vert\boldsymbol r\vert^{-3}\boldsymbol r)&=0\end{align*}
\begin{align*}\boldsymbol\nabla^2\vert\boldsymbol r\vert^{-1}&=0\end{align*}
【前ページ】 【次ページ】
HOME > 物理数学 > ベクトル解析 >発散