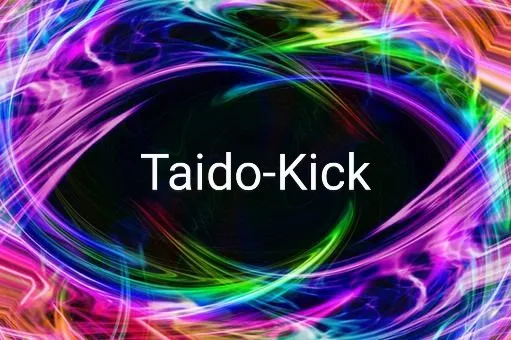HOME > 電磁気学 > 静磁場 > E-H対応とE-B対応
【前ページ】 【次ページ】
本ページでは…
本ページでは、磁気現象を「磁荷によって説明するE-H対応」と「電流によって説明するE-B対応」について説明する。
内容
E-H対応とE-B対応
磁気現象を説明する際に、「磁荷によって説明するE-H対応」と「電流によって説明するE-B対応」がある。どちらも考え方が異なるだけで、理論としてはほぼ等価である。
E-H対応
古くから知られている磁気現象としては磁石があり、電気現象の源である電荷のように、磁荷と呼ばれるものが存在し、その磁荷が磁気現象を引き起こすと考えられていた。つまり、電気現象のときと同様(以前のページを参照)に、離れた2つの磁荷の間に力が働くとき、「①磁荷が源場である磁束密度を作る」、「②源場から力場が生じる」、「③力場である磁場が磁荷に力を与える」という3ステップで力が働くと考えられる。
電気現象と磁気現象を比較すると、源場は電場\(\boldsymbol E\)と磁場\(\boldsymbol H\)、力場は電束密度\(\boldsymbol D\)と磁束密度\(\boldsymbol B\)であり、電場\(\boldsymbol E\)と磁場\(\boldsymbol H\)が対応するしていることから、この理論をE-H対応という。
磁石を分割しても、再度N極とS極が生じ、単体の磁荷を取り出すことはできない、つまり、モノポール(磁気単極子)は存在せず、常にダイポール(磁気双極子)として存在する。また、厳密には磁気双極子としても存在しておらず、電子が作るループ電流が磁気双極子のように振舞っている。そのため、磁荷の存在を前提とするE-H対応では磁気現象の説明が難しいのでは?と思うかもしれない。しかし、正負の磁荷が無限小接近したときの磁気双極子が作る磁場は、ループ電流が作る磁場と全く区別が付かないため、「磁荷が磁気現象の源と考えるE-H対応」と次に述べる「電流が磁気現象の源と考えるE-B対応」は等価である。
E-H対応については次ページから詳細を述べていく。
E-B対応
1820年にエルステッドは電流が流れるとその周りの方位磁針が動くことに気づき、電流が磁気現象を引き起こすことを発見した。また、同年にアンペールは電流同士に力が働く様子を観察し、以後、磁気現象の源は電流としても説明されてきた。具体的には、離れた2つの電流の間に力が働くとき、「①電流が源場である磁場を作る」、「②源場から力場が生じる」、「③力場である磁束密度が電流に力を与える」という3ステップで力が働くと考えられる。
磁気現象と電気現象を比較すると、源場は電場\(\boldsymbol E\)と磁束密度\(\boldsymbol B\)、力場は電束密度\(\boldsymbol D\)と磁場\(\boldsymbol H\)であり、電場\(\boldsymbol E\)と磁束密度\(\boldsymbol B\)が対応するしていることから、この理論をE-B対応という。
古典物理学として考えるだけなら、磁気現象の源は電子のループ電流と考えても良いが、実際には電子が環運動すると電磁波を放出し安定した軌道を回れないため、厳密には量子力学を用いて説明する必要がある。
E-B対応については後のページから詳細を述べていく。
なぜ源場と力場が入れ替わるか
E-H対応とE-B対応で源場と力場が入れ替わっているが、単純にそう定義しただけではなく、ちゃんと意味がある。このことについては後のページで詳細を述べる。
次ページから…
次ページでは、真磁荷は自由に移動したり外部に取り出したりできる磁荷であるが、磁化で生じた分極磁荷は自由に移動したり外部に取り出したりできない磁荷であることを確認する。
【前ページ】 【次ページ】