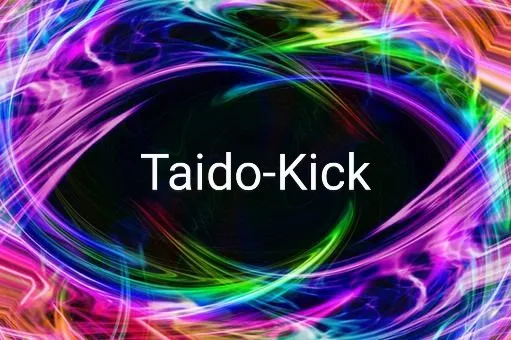HOME > 電磁気学 > 動磁場 > ファラデーの電磁誘導の法則
【前ページ】 【次ページ】
本ページでは…
本ページでは、導体である閉曲線\(C\)に生じる起電力\(\varepsilon\)が閉曲線\(C\)に囲われた面\(S\)を貫く磁束\(\varPhi\)の時間変化率に比例するというファラデーの電磁誘導の法則
を導く。
内容
電磁誘導
1831年にマイケル・ファラデーは磁束を変化させると導体に起電力が生じることを発見した。導体である閉曲線\(C\)に生じる起電力\(\varepsilon\)は、閉曲線\(C\)に囲われた面\(S\)を貫く磁束\(\varPhi\)の時間変化率に比例しており、この法則
をファラデーの電磁誘導の法則という。ここで、面\(S\)を貫く磁束\(\varPhi\)の向きを右ネジが進む向きとしたとき、右ネジが進むときに回る向きに沿って閉曲線\(C\)上に起電力\(\varepsilon\)が生じる。
磁束を作る磁石と導体の運動は相対的であるため、導体を固定して磁石を動かしても、磁石を固定して導体を動かしても等価である。
ファラデーの電磁誘導の法則の導出
ファラデーの電磁誘導の法則を導出する。ここでは、磁束\(\varPhi\)は時間変化せず、導体である閉曲線\(C\)が動くと考える。
閉曲線\(C\)上にある点を位置ベクトル\(\boldsymbol r\)で表し、その点が速度\(\boldsymbol v(\boldsymbol r)\)で動いているとすると、閉曲線\(C\)上に存在する電荷\(q\)の粒子はローレンツ力
を受ける(以前のページを参照)。そして、電場\(\boldsymbol E(\boldsymbol r)\)とローレンツ力\(\boldsymbol F(\boldsymbol r)\)の関係は
であるため、閉曲線\(C\)上の電場\(\boldsymbol E(\boldsymbol r)\)は
となる。そして、起電力\(\varepsilon\)は電場\(\boldsymbol E\)の線積分で求めることができるため、大きさが微小距離\(dl\)の値に等しく、向きが微小距離\(dl\)の接線の向きに等しい線素\(d\boldsymbol l\)を定義したとき、閉曲線\(C\)上の起電力\(\varepsilon\)は
となる。この閉曲線\(C\)の線積分において、経路の回り方で2つのパターンが存在するが、貫く磁束の向きを右ネジが進む向きとした際に、右ネジが進むときに回る向きの経路で線積分を行なうとする。また、線素\(d\boldsymbol l\)の向きは経路の回る向きとしておく。
イメージしやすいように次の例を考えてみる。
点\(A(0,0,0)\)→点\(B(1,0,0)\)→点\(C(1,1,0)\)→点\(D(0,1,0)\)→点\(A\)を通る閉曲線\(C\)において、磁束が\(z\)軸の正方向に貫いており、辺\(BC\)のみを\(x\)軸の正方向に速度\(v \)で微小時間\(dt\)だけ移動させるとしたとき起電力\(\varepsilon\)を求めてみる。
貫く磁束の向きを右ネジが進む向きとした際に、右ネジが進むときに回る向きの経路で線積分を行なうため、式(5)の線積分の経路は点\(A\)→点\(B\)→点\(C\)→点\(D\)→点\(A\)となり、線素\(d\boldsymbol l\)の向きはこの経路に沿った向きとなる。また、辺\(BC\)のみ移動するため、式(5)は経路\(B\rightarrow C\)のみを考えればよく、起電力\(\varepsilon\)は
となる。
次に、閉曲線\(C\)が速度\(\boldsymbol v(\boldsymbol r)\)で微小時間\(dt\)だけ動いた際に、閉曲線\(C\)上の線素\(d\boldsymbol l\)が掃く平行四辺形の微小面積\(dS’\)は
となり、大きさが微小面積\(dS’\)の値に等しく、向きが微小面積\(dS’\)の法線の向きに等しい面積素\(d\boldsymbol S’\)は
となる。磁束の面密度である磁束密度\(\boldsymbol B\)と面積素\(d\boldsymbol S’\)の内積をとると微小面積\(dS’\)を法線の向きに貫く磁束の量となり、閉曲線\(C\)において線積分したもの
は微小時間\(dt\)の間に閉曲線\(C\)に囲われた面\(S\)を貫く磁束の変化量\(d\varPhi\)であり、
4行目への変形ではベクトルのスカラー三重積の性質
を用いた。
となる。ここで、式(5)と同様に、貫く磁束の向きを右ネジが進む向きとした際に、右ネジが進むときに回る向きの経路で線積分を行ない、線素\(d\boldsymbol l\)の向きは経路の回る向きとしておく。
イメージしやすいように次の例を考えてみる。
点\(A(0,0,0)\)→点\(B(1,0,0)\)→点\(C(1,1,0)\)→点\(D(0,1,0)\)→点\(A\)を通る閉曲線\(C\)において、磁束が\(z\)軸の正方向に貫いており、辺\(BC\)のみを\(x\)軸の正方向に速度\(v \)で微小時間\(dt\)だけ移動させるとしたとき貫く磁束の変化量\(d\varPhi\)を求めてみる。
貫く磁束の向きを右ネジが進む向きとした際に、右ネジが進むときに回る向きの経路で線積分を行なうため、式(9)の線積分の経路は点\(A\)→点\(B\)→点\(C\)→点\(D\)→点\(A\)となり、線素\(d\boldsymbol l\)の向きはこの経路に沿った向きとなる。また、辺\(BC\)のみ移動するため、式(9)は経路\(B\rightarrow C\)のみを考えればよく、磁束の変化量\(d\varPhi\)は
となる。
ここで、線素\(d\boldsymbol l\)が掃く平行四辺形の面積素\(d\boldsymbol S’\)は
となり、磁束密度\(\boldsymbol B\)との内積を線積分したものは貫く磁束の変化量\(d\varPhi\)になるが、もし面積素\(d\boldsymbol S’\)を
と置いていたら、磁束密度\(\boldsymbol B\)との内積を線積分したものは貫く磁束の変化量\(d\varPhi\)に負号を付けたものになってしまう。
最後に、式(9)の両辺を微小時間\(dt\)で割ると
となり、この式と式(5)よりファラデーの電磁誘導の法則
が導かれる。
磁気力線ではなく磁束を用いる理由
ファラデーの電磁誘導の法則において、磁束を用いて表した。磁気力線を用いて表さなかった理由は、電磁誘導という現象は動く電荷(電流)に力場が力を及ぼすと考えるE-B対応の現象であり、E-B対応における力場は磁束密度だからである(以前のページを参照)。
【前ページ】 【次ページ】