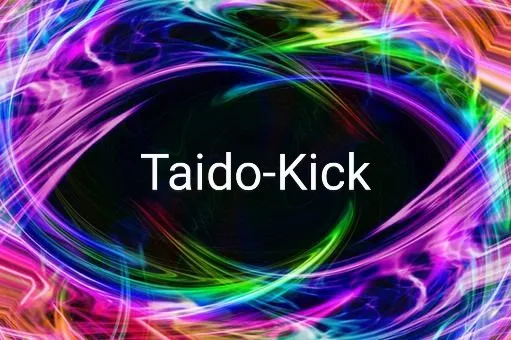HOME > 物理数学 > ベクトル解析 >回転
【前ページ】 【次ページ】
本ページでは…
本ページでは、回転がベクトル場の各点のベクトル値を、向きが「その点に生じている渦の回転軸(右手系)の向き」で大きさが「渦の強さ」であるベクトルに置き換える作用素であることをみる。また、3次元デカルト座標では回転\(\boldsymbol\nabla\)は
\begin{align*}\boldsymbol\nabla×=\left(\frac{\partial }{\partial x},\frac{\partial }{\partial y},\frac{\partial }{\partial z}\right)×\end{align*}
となることを求める。
前ページまで…
前ページでは、以下の発散の公式を求めた。
\begin{align*}\boldsymbol \nabla\cdot(\boldsymbol\nabla×\boldsymbol f)=0\end{align*}
\begin{align*}\boldsymbol\nabla\cdot\boldsymbol r&=3\end{align*}
\begin{align*}\boldsymbol\nabla\cdot(\vert\boldsymbol r\vert^{-3}\boldsymbol r)&=0\end{align*}
\begin{align*}\boldsymbol\nabla^2\vert\boldsymbol r\vert^{-1}&=0\end{align*}
内容
循環と循環密度
ベクトル場\(\boldsymbol f\)において、ある閉曲線\(C\)が与えられたとき、閉曲線\(C\)に沿ってベクトル場を積算した値を循環という。、大きさが微小距離\(dl\)の値に等しく、向きが微小距離\(dl\)の接線の向きに等しい線素\(d\boldsymbol l\)を用いると、循環は次のような線積分で表される。
\begin{align*}\int_C \boldsymbol f\cdot d\boldsymbol l\tag{1}\end{align*}
循環を求める際に、閉曲線\(C\)に沿ってどちら回りに求めるかによって循環の符号が逆転してしまうため、通常は閉曲線\(C\)が作る曲面\(S\)の法線ベクトルの向きに右ネジが進むとした際に、右ネジが進むときに回る向きに循環を求める。
閉曲線\(C\)が作る曲面\(S\)の面積値で循環を割った単位面積あたりの循環を循環密度という。また、閉曲線\(C\)を無限に小さくしたときの循環を微小循環といい、閉曲線\(C\)が作る微小面積\(dS\)の面積値で割った単位面積あたりの循環を微小循環密度という。
循環密度の値がゼロであれば閉曲線\(C\)に沿って渦は生じていないが、ゼロでなければ閉曲線\(C\)に沿って渦が生じており、循環密度は渦の強さを表す。
回転
ベクトル場の各点におけるベクトル値を、向きが「その点に生じている渦の回転軸(右手系)の向き」で大きさが「渦の強さ」である回転ベクトルに対応させる作用素(演算子)を回転といい、\(\boldsymbol\nabla×\)または\(\text{rot}\)で表す。この回転によって、ベクトル場は回転ベクトル場と呼ばれるベクトル場に変換され、ベクトル場を\(\boldsymbol f\)とすると回転ベクトル場は\(\boldsymbol \nabla ×\boldsymbol f\)と表される。つまり、常に回転はベクトル場に作用し、作用後はベクトル場となる。
渦の強さを表す循環密度を用いて回転ベクトルを厳密に表すと、向きは「微小循環密度が最大となる微小面積の法線の向き」で大きさは「最大となる微小循環密度の大きさ」となり、この回転ベクトルを求めるには、\(x\),\(y\),\(z\)軸の正方向を法線とする微小面積における微小循環密度を求め、それらを成分とするようなベクトルを作ればよい。
3次元デカルト座標における回転
3次元デカルト座標における回転が
\begin{align*}\boldsymbol\nabla×=\left(\frac{\partial }{\partial x},\frac{\partial }{\partial y},\frac{\partial }{\partial z}\right)×\tag{2}\end{align*}
となること、言い換えると、ベクトル場が\(\boldsymbol f=(f_x,f_y,f_z)\)のときに回転ベクトル\(\boldsymbol\nabla ×\boldsymbol f\)
\begin{align*}\boldsymbol \nabla×\boldsymbol f=\left(\frac{\partial f_z}{\partial y}-\frac{\partial f_y}{\partial z},\frac{\partial f_x}{\partial z}-\frac{\partial f_z}{\partial x},\frac{\partial f_y}{\partial x}-\frac{\partial f_x}{\partial y}\right)\tag{3}\end{align*}
の向きが「微小循環密度が最大となる微小面積の法線の向き」で大きさが「最大となる微小循環密度の大きさ」であることを確認する。
初めに、\(z\)軸の向きに垂直な正方形の面\(dx×dy\)が点\((x,y,z)\)を中心に配置されていると考える。このとき、\(z\)軸の正方向を右手系となる回転軸として正方形の頂点を次のように移動
\begin{align*}&①(x-dx/2,y-dy/2,z)\rightarrow(x+dx/2,y-dy/2,z)\\&②(x+dx/2,y-dy/2,z)\rightarrow(x+dx/2,y+dy/2,z)\\&③(x+dx/2,y+dy/2,z)\rightarrow(x-dx/2,y+dy/2,z)\\&④(x-dx/2,y+dy/2,z)\rightarrow(x-dx/2,y-dy/2,z)\end{align*}
した際の循環は
\begin{align*}&f_x(x,y-dy/2,z)dx+f_y(x+dx/2,y,z)dy-f_x(x,y+dy/2,z)dx-f_y(x-dx/2,y,z)dy\\=&(f_y(x+dx/2,y,z)-f_y(x-dx/2,y,z))dy-(f_x(x,y+dy/2,z)-f_x(x,y-dy/2,z))dx\\=&\frac{f_y(x+dx/2,y,z)-f_y(x-dx/2,y,z)}{dx}dxdy+\frac{f_x(x,y+dy/2,z)-f_x(x,y-dy/2,z)}{dy}dxdy\\=&\frac{\partial f_y}{\partial x}dxdy-\frac{\partial f_x}{\partial y}dxdy\tag{4}\end{align*}
循環とは閉曲線\(C\)に沿ってベクトル場を積算した値
\begin{align*}\int_C \boldsymbol f\cdot d\boldsymbol l\end{align*}
であるため、それぞれの経路で「線素\(d\boldsymbol l\)」と「ベクトル場\(\boldsymbol f\)」の内積で循環を求めている。「線素\(d\boldsymbol l\)」は
\begin{align*}&経路①(dx,0,0)\\&経路②(0,dy,0)\\&経路③(-dx,0,0)\\&経路④(0,-dy,0)\end{align*}
であり、「ベクトル場
\begin{align*}\boldsymbol f(x,y,z)=(f_x(x,y,z),f_y(x,y,z),f_z(x,y,z))\end{align*}
」は始点と終点の平均値として中間点の値
\begin{align*}&経路①\frac{\boldsymbol f(x-dx/2,y-dy/2,z)+\boldsymbol f(x+dy,y-dy/2,z)}{2}\simeq\boldsymbol f(x,y-dy/2,z)\\&経路②\frac{\boldsymbol f(x+dx/2,y-dy/2,z)+\boldsymbol f(x+dy,y+dy/2,z)}{2}\simeq\boldsymbol f(x+dx/2,y,z)\\&経路③\frac{\boldsymbol f(x+dx/2,y+dy/2,z)+\boldsymbol f(x-dy,y+dy/2,z)}{2}\simeq\boldsymbol f(x,y+dy/2,z)\\&経路④\frac{\boldsymbol f(x-dx/2,y+dy/2,z)+\boldsymbol f(x-dy,y-dy/2,z)}{2}\simeq\boldsymbol f(x-dx/2,y,z)\end{align*}
を用いている。
となる。また、正方形の面積は\(dxdy\)であるため、微小面積における単位面積当たりの循環である微小循環密度は
\begin{align*}\frac{\partial f_y}{\partial x}-\frac{\partial f_x}{\partial y}\tag{5}\end{align*}
となる。以上より、\(z\)軸に垂直な正方形の面\(dx×dy\)において、点に球を置いて回転したときに、右手系となる回転軸の向きは\(z\)軸の正方向となり、その大きさは
\begin{align*}\frac{\partial f_y}{\partial x}-\frac{\partial f_x}{\partial y}\tag{5}\end{align*}
となる。
\(z\)軸に垂直な正方形の面\(dx×dy\)と同様に、\(x\)軸に垂直な正方形の面\(dy×dz\)において、\(x\)軸の正方向を右手系となる回転軸として正方形の頂点を移動して求めた微小循環密度は
\begin{align*}\frac{\partial f_z}{\partial y}-\frac{\partial f_y}{\partial z}\tag{6}\end{align*}
となり、\(x\)軸に垂直な正方形の面\(dy×dz\)において、点に球を置いて回転したときに、右手系となる回転軸の向きは\(x\)軸の正方向となり、その大きさは
\begin{align*}\frac{\partial f_y}{\partial x}-\frac{\partial f_x}{\partial y}\tag{6}\end{align*}
となる。
また、\(y\)軸に垂直な正方形の面\(dz×dx\)において、\(y\)軸の正方向を右手系となる回転軸として正方形の頂点を移動して求めた微小循環密度は
\begin{align*}\frac{\partial f_x}{\partial z}-\frac{\partial f_z}{\partial x}\tag{7}\end{align*}
となり、\(y\)軸に垂直な正方形の面\(dz×dx\)において、点に球を置いて回転したときに、右手系となる回転軸の向きは\(y\)軸の正方向となり、その大きさは
\begin{align*}\frac{\partial f_x}{\partial z}-\frac{\partial f_z}{\partial x}\tag{7}\end{align*}
となる。
それぞれの軸方向の微小循環密度を成分に持つベクトル
\begin{align*}\left(\frac{\partial f_z}{\partial y}-\frac{\partial f_y}{\partial z},\frac{\partial f_x}{\partial z}-\frac{\partial f_z}{\partial x},\frac{\partial f_y}{\partial x}-\frac{\partial f_x}{\partial y}\right)\tag{2}\end{align*}
は向きが「微小循環密度が最大となる微小面積の法線の向き」であり、大きさが「最大となる微小循環密度の大きさ」であるから、これが回転ベクトルである。
次ページから…
次ページでは、以下の回転の公式を求める。
\begin{align*}\boldsymbol\nabla×\boldsymbol r&=\boldsymbol 0\end{align*}
\begin{align*}\boldsymbol\nabla×(g\boldsymbol f)&=\boldsymbol\nabla g×\boldsymbol f+g\boldsymbol\nabla×\boldsymbol f\end{align*}
\begin{align*}\boldsymbol\nabla×(\boldsymbol \nabla×\boldsymbol f)=\boldsymbol\nabla(\boldsymbol \nabla\cdot\boldsymbol f)-(\boldsymbol\nabla\cdot\boldsymbol\nabla) \boldsymbol f\end{align*}
【前ページ】 【次ページ】
HOME > 物理数学 > ベクトル解析 >回転