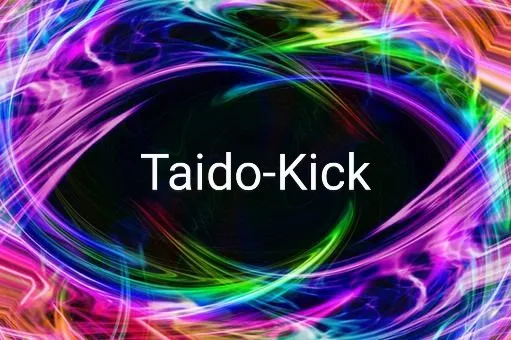HOME > 電磁気学 > マクスウェル方程式 > マクスウェル方程式の導出
【前ページ】 【次ページ】
本ページでは…
本ページでは、マクスウェル方程式
\begin{align*}\boldsymbol \nabla \cdot\boldsymbol B&=0\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ (\text{div}\boldsymbol B=0)\\\boldsymbol\nabla×\boldsymbol E&=-\frac{\partial \boldsymbol B}{\partial t}\ \ \ \ \ \ \ \left(\text{rot}\boldsymbol E=-\frac{\partial \boldsymbol B}{\partial t}\right)\\\boldsymbol\nabla\cdot\boldsymbol D&=\rho\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ (\text{div}\boldsymbol D=\rho)\\\boldsymbol\nabla×\boldsymbol H&=\boldsymbol j+\frac{\partial \boldsymbol D}{\partial t}\ \ \ \left(\text{rot}\boldsymbol H=\boldsymbol j+\frac{\partial \boldsymbol D}{\partial t}\right)\end{align*}
または
\begin{align*}\int_S\boldsymbol B\cdot d\boldsymbol S&=0\\\int_C\boldsymbol E\cdot d\boldsymbol l&=-\int_S\frac{\partial \boldsymbol B}{\partial t}\cdot d\boldsymbol S\\\int_S \boldsymbol D\cdot d\boldsymbol S&=q\\\int_C\boldsymbol H\cdot d\boldsymbol l&=\int_S \left(\boldsymbol j+\frac{\partial \boldsymbol D}{\partial t}\right)\cdot d\boldsymbol S\end{align*}
を導出し、方程式の構成について調べる。
内容
マクスウェル方程式とは
古典電磁気学の基礎方程式をまとめた以下の四つの式
\begin{align*}\boldsymbol \nabla \cdot\boldsymbol B&=0\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ (\text{div}\boldsymbol B=0)\tag{1}\\\boldsymbol\nabla×\boldsymbol E&=-\frac{\partial \boldsymbol B}{\partial t}\ \ \ \ \ \ \ \left(\text{rot}\boldsymbol E=-\frac{\partial \boldsymbol B}{\partial t}\right)\tag{2}\\\boldsymbol\nabla\cdot\boldsymbol D&=\rho\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ (\text{div}\boldsymbol D=\rho)\tag{3}\\\boldsymbol\nabla×\boldsymbol H&=\boldsymbol j+\frac{\partial \boldsymbol D}{\partial t}\ \ \ \left(\text{rot}\boldsymbol H=\boldsymbol j+\frac{\partial \boldsymbol D}{\partial t}\right)\tag{4}\end{align*}
または
\begin{align*}\int_S\boldsymbol B\cdot d\boldsymbol S&=0\tag{5}\\\int_C\boldsymbol E\cdot d\boldsymbol l&=-\int_S\frac{\partial \boldsymbol B}{\partial t}\cdot d\boldsymbol S\tag{6}\\\int_S \boldsymbol D\cdot d\boldsymbol S&=q\tag{7}\\\int_C\boldsymbol H\cdot d\boldsymbol l&=\int_S \left(\boldsymbol j+\frac{\partial \boldsymbol D}{\partial t}\right)\cdot d\boldsymbol S\tag{8}\end{align*}
をマクスウェル方程式という。初めの4つの式は微分形、後の4つの式は積分形となっており、どちらも等価な式である。ここで、\(\boldsymbol B\)は磁束密度、\(\boldsymbol E\)は電場、\(\boldsymbol D\)は電束密度、\(\boldsymbol H\)は磁場、\(\rho\)は電荷密度、\(\boldsymbol j\)は電流密度、\(q\)は電荷である。
電場\(\boldsymbol E\)と電束密度\(\boldsymbol D\)、または磁場\(\boldsymbol H\)と磁束密度\(\boldsymbol B\)は構成方程式によって結ばれており、E-H対応における構成方程式は
\begin{align*}\boldsymbol E&=\frac{1}{\epsilon_0}(\boldsymbol D-\boldsymbol P)\tag{9}\\\boldsymbol H&=\frac{1}{\mu_0}(\boldsymbol B-\boldsymbol P_{\text m})\tag{10}\end{align*}
であり、E-B対応における構成方程式は
\begin{align*}\boldsymbol E&=\frac{1}{\epsilon_0}(\boldsymbol D-\boldsymbol P)\tag{9}\\\boldsymbol B&=\mu_0(\boldsymbol H+\boldsymbol M)\tag{11}\end{align*}
である。ここで、\(\boldsymbol P\)は分極、\(\boldsymbol P_\text m\)は磁気分極、\(\boldsymbol M\)は磁化、\(\epsilon_0\)は真空の誘電率、\(\mu_0\)は真空の透磁率である。
マクスウェル方程式は電磁気学における基礎方程式を全て網羅している訳では無く、ローレンツ力の式(後のページを参照)
\begin{align*}\boldsymbol F=q\boldsymbol E+q\boldsymbol v×\boldsymbol B\end{align*}
をマクスウェル方程式から導くことはできない。そのため、マクスウェル方程式とローレンツ力の式を合わせて電磁気学の基礎方程式である。
磁束保存の式
\begin{align*}\boldsymbol \nabla \cdot\boldsymbol B&=0\ \ \ \ (\text{div}\boldsymbol B=0)\tag{1}\end{align*}
または
\begin{align*}\int_S\boldsymbol B\cdot d\boldsymbol S&=0\tag{5}\end{align*}
を磁束保存の式という。この式は、磁束には起点や終点がないループ線であること、言い換えると、あらゆる閉曲面において磁束の流入量と流出量は等しいことを示している。これは、磁気単極子(モノポール)が存在しないことを表し、代わりに磁束の発生源は磁気双極子(ダイポール)であることを表す。
磁束保存の式については次ページで導出する。
ファラデー-マクスウェルの式
\begin{align*}\boldsymbol \nabla×\boldsymbol E&=-\frac{\partial \boldsymbol B}{\partial t}\ \ \ \ \left(\text{rot}\boldsymbol E=-\frac{\partial \boldsymbol B}{\partial t}\right)\tag{2}\end{align*}
または
\begin{align*}\int_C\boldsymbol E\cdot d\boldsymbol l&=-\int_S\frac{\partial \boldsymbol B}{\partial t}\cdot d\boldsymbol S\tag{6}\end{align*}
をファラデー-マクスウェルの式という。この式は、磁束密度\(\boldsymbol B\)の時間変化があるところにはループしている電場\(\boldsymbol E\)があることを示し、導線は動かずに磁石が動く場合のファラデーの電磁誘導の法則に相当する。
ファラデー-マクスウェルの式(2)または(6)は、アンペール-マクスウェルの式(4)または(8)と類似点が多いが、ひとつ大きく違うところは電流\(\boldsymbol j\)に相当する磁流というものが存在していないことである。
ファラデー-マクスウェルの式については次々ページで導出する。
マクスウェル-ガウスの式
\begin{align*}\boldsymbol \nabla\cdot\boldsymbol D&=\rho\ \ \ \ (\text{div}\boldsymbol D=\rho)\tag{3}\end{align*}
または
\begin{align*}\int_S \boldsymbol D\cdot d\boldsymbol S&=Q_f\tag{7}\end{align*}
をマクスウェル-ガウスの式という。この式は、電束の源は真電荷\(Q_\text f\)であり、真電荷の無いところでは電束が保存することを示している。
マクスウェル-ガウスの式については後のページで導出する。
アンペール-マクスウェルの式
\begin{align*}\boldsymbol \nabla×\boldsymbol H&=\boldsymbol j+\frac{\partial \boldsymbol D}{\partial t}\ \ \ \ \left(\text{rot}\boldsymbol H=\boldsymbol j+\frac{\partial \boldsymbol D}{\partial t}\right)\tag{4}\end{align*}
または
\begin{align*}\int_C\boldsymbol H\cdot d\boldsymbol l&=\int_S \left(\boldsymbol j+\frac{\partial \boldsymbol D}{\partial t}\right)\cdot d\boldsymbol S\tag{8}\end{align*}
をアンペール-マクスウェルの式という。この式は電流\(\int_S\boldsymbol j\cdot d\boldsymbol S\)または変位電流\(\int_S\frac{\partial\boldsymbol D}{\partial t}\cdot d\boldsymbol S\)の周りにはループしている磁場\(\boldsymbol H\)があることを示し、電流によって磁場\(\boldsymbol H\)が生じることを表したアンペールの法則(以前のページを参照)に変位電流によって生じる磁場を加えたものである。
ここで、変位電流とは電束密度\(\boldsymbol D\)の閉曲面\(S\)における法線成分の面積分が時間的に変位するときに生じる電流であり、電荷の移動で生じる通常の電流とは異なる。変位電流の例としてコンデンサーがあり、コンデンサーに導線を繋ぎ放電させるとき、コンデンサーの電極間に変位電流が生じて閉回路が作られる。また、雷も変位電流の例であり、落雷によって雷雲から放電する際に、落雷とは別に雷雲と地面の間に変位電流が生じて閉回路が作られる。
アンペール-マクスウェルの式については後のページで導出する。
力場と源場
E-H対応において、力場は電場\(\boldsymbol E\)と磁場\(\boldsymbol H\)であり、源場は電束密度\(\boldsymbol D\)と磁束密度\(\boldsymbol B\)であったため、それぞれが対応するように各式をまとめると
\begin{align*}\boldsymbol\nabla×\boldsymbol E&=-\frac{\partial \boldsymbol B}{\partial t}\tag{2}\\\boldsymbol\nabla×\boldsymbol H&=\boldsymbol j+\frac{\partial \boldsymbol D}{\partial t}\tag{4}\end{align*}
と
\begin{align*}\boldsymbol \nabla \cdot\boldsymbol B&=0\tag{1}\\\boldsymbol\nabla\cdot\boldsymbol D&=\rho\tag{3}\end{align*}
となって、式構造に類似性が見てとれる。また、式(2)と式(4)を変形すると
\begin{align*}\frac{\partial \boldsymbol B}{\partial t}&=-\boldsymbol\nabla×\boldsymbol E\tag{9}\\\frac{\partial \boldsymbol D}{\partial t}&=\boldsymbol\nabla×\boldsymbol H-\boldsymbol j\tag{10}\end{align*}
となって、式(1)と式(3)は初期条件であり、式(9)と式(10)は時間発展の式と捉えることができる。
一方、E-B対応において、力場は電場\(\boldsymbol E\)と磁束密度\(\boldsymbol B\)であり、源場は電束密度\(\boldsymbol D\)と磁場\(\boldsymbol H\)であったため、それぞれが対応するように各式をまとめると
\begin{align*}\boldsymbol \nabla \cdot\boldsymbol B&=0\tag{1}\\\boldsymbol\nabla×\boldsymbol E&=-\frac{\partial \boldsymbol B}{\partial t}\tag{2}\end{align*}
と
\begin{align*}\boldsymbol\nabla\cdot\boldsymbol D&=\rho\tag{3}\\\boldsymbol\nabla×\boldsymbol H&=\boldsymbol j+\frac{\partial \boldsymbol D}{\partial t}\tag{4}\end{align*}
となって、E-H対応ほど式構造に類似性はみられない。しかし、E-H対応におけるマクスウェル方程式の源場に関する式(1)と式(3)を見ても何が源場を作っているのか分かり辛かったが、E-B対応におけるマクスウェル方程式の源場に関する式(3)と式(4)を見ればひと目で電荷や電流が源場を作り出していることが分かる。そして、力場に関する式(1)と式(2)は拘束条件となって電磁場の形を決めていると解釈できる。
流れの保存の式
マクスウェル方程式の式(4)の全体に発散を作用させると
\begin{align*}\boldsymbol \nabla\cdot(\boldsymbol\nabla×\boldsymbol H)&=\boldsymbol \nabla\cdot\boldsymbol j+\boldsymbol \nabla\cdot\frac{\partial \boldsymbol D}{\partial t}\\\rightarrow\boldsymbol \nabla\cdot\boldsymbol j+\frac{\partial \rho}{\partial t}&=0\tag{11}\end{align*}
2行目への変形では、回転の発散がゼロになること(以前のページを参照)
\begin{align*}\boldsymbol \nabla\cdot(\boldsymbol\nabla×\boldsymbol f)=0\end{align*}
と、式(3)を用いた。
となって流れの保存の式が導かれる。
電荷の保存
流束密度である電流密度\(\boldsymbol j\)の発散\(\boldsymbol \nabla\cdot\boldsymbol j\)は流束である電流の湧き出しを表す(以前のページを参照)ため、流れの保存の式(11)
\begin{align*}\boldsymbol \nabla\cdot\boldsymbol j+\frac{\partial \rho}{\partial t}&=0\tag{11}\end{align*}
が示すことは、「単位体積内に存在する電荷の時間減少率\(-\frac{\partial \rho}{\partial t}\)」が「単位体積から湧き出る電流\(\boldsymbol \nabla\cdot\boldsymbol j\)」に等しいことを意味し、理由もなく電荷が突然現れたり消えたりすることはないということである。
流れの保存の式(11)から電荷の保存式を導くことができる。流れの保存の式(11)を変形して体積積分すると
\begin{align*}\int \frac{\partial \rho}{\partial t}\ d^3\boldsymbol x&=-\int\boldsymbol\nabla\cdot \boldsymbol j\ d^3\boldsymbol x\\\rightarrow\frac{d}{dt}\int \rho\ d^3\boldsymbol x&=-\int \boldsymbol\nabla\cdot \boldsymbol j \ d^3\boldsymbol x\tag{12}\end{align*}
式(12)の2行目への変形において偏微分から全微分に変わっている理由について述べておく。
電荷密度\(\rho\)は座標\((x,y,z)\)と時間\(t\)を変数にする関数であるため、式(12)の1行目では時間\(t\)に関して偏微分で表記している。
一方、電荷\(\int \rho\ d^3\boldsymbol x\)は電荷密度\(\rho\)を体積積分して求めているため、電荷\(\int \rho\ d^3\boldsymbol x\)は時間\(t\)を変数にする関数ではあるが、もはや座標\((x,y,z)\)を変数にした関数ではなく、関数である電荷密度\(\rho\)の形によって値が決まる汎関数となっている。そのため、式(12)の2行目では時間\(t\)に関して全微分で表記している。
となり、発散定理(以前のページを参照)
\begin{align*}\int \ \boldsymbol\nabla\cdot \boldsymbol j\ d^3\boldsymbol x=\int_S \boldsymbol j\cdot d\boldsymbol S\tag{13}\end{align*}
を用いると
\begin{align*}\frac{d}{dt}\int \rho\ d^3\boldsymbol x=-\int_S \boldsymbol j\cdot d\boldsymbol S\tag{14}\end{align*}
と表すことができる。最後に、「どの時刻においても、空間の無限遠では常に電流密度\(\boldsymbol j\)がゼロになる」ことを用いると、式(14)の右辺において無限遠で面積分を行なえばゼロとなり、次式
\begin{align*}\frac{d}{dt}\int \rho\ d^3\boldsymbol x=0\tag{15}\end{align*}
が成り立つことが分かる。この式が電荷の保存式であり、全空間と全時間において全電荷\(\int \rho\ d^3\boldsymbol x\)は変化しないことを表す。
次ページから…
次ページでは、マクスウェル方程式を構成する磁束保存の式
\begin{align*}\boldsymbol \nabla \cdot\boldsymbol B&=0\ \ \ \ (\text{div}\boldsymbol B=0)\end{align*}
または
\begin{align*}\int_S\boldsymbol B\cdot d\boldsymbol S&=0\end{align*}
を導く。また、磁束保存の式から磁場\(\boldsymbol H\)の定義や磁気分極\(\boldsymbol P_\text m\)・磁化\(\boldsymbol M\)の定義、そして、クーロンの法則(静磁場)が導かれることを確認する。
【前ページ】 【次ページ】
HOME > 電磁気学 > マクスウェル方程式 >マクスウェル方程式の導出