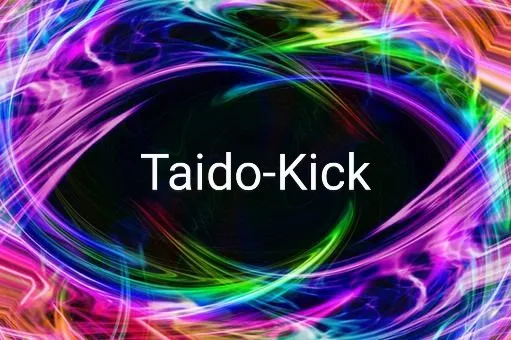【前ページ】 【次ページ】
本ページでは…
本ページでは、真電荷は自由に移動したり外部に取り出したりできる電荷であるが、誘電分極で生じた分極電荷は自由に移動したり外部に取り出したりできない電荷であることを確認する。
内容
電荷
電気現象を引き起こす源を電荷と呼び、その量を電荷量と呼ぶ。電荷量は正または負の値を取り、電荷量が正である電荷を正電荷といい、電荷量が負である電荷を負電荷という。
電荷の単位はクーロン\(\text C\)で表され、\(1\text C\)の電荷量は\(1\text A\)の電流が導線の断面を\(1\)秒に通過する電荷量として定義される。ここで、\(1\text A\)は真空中に \(1\text m\)の間隔で平行に配置された無限に長い二本の導線に、長さ \(1\text m\)につき\(2×10^{-7}\text N\)の力が及ぼし合うときの導線に流した電流と定義される。
電荷は真電荷と分極電荷に分けることができ、この分類はとても重要になってくるため、それぞれについて次から述べていく。
真電荷
真電荷(あるいは自由電荷)とは、自由に移動したり外部に取り出したりできる電荷である。真電荷の例として、電極に存在する電荷や、コンデンサーに蓄えられた電荷がある。
分極電荷
大きさの等しい正負の電荷対を電気双極子といい、電気双極子には永久双極子と誘起双極子がある。永久双極子とは分子構造や構成原子の電気陰性度差によって電気双極子となっているものであり、例としては水分子や塩化水素分子がある。誘起双極子とは真電荷を近づけると構成する原子核や電子の位置が平均的な位置からズレて電気双極子となるものであり、例としてはメタン分子や二酸化炭素分子がある。
誘電体(または絶縁体)に真電荷が近づいたとき、誘電体を構成する無数の電気双極子(永久双極子と誘起双極子)が整列する現象を誘電分極という。誘電分極した電気双極子の電荷は隣の電気双極子の電荷によって互いに打ち消し合うが、誘電体の表面では打ち消し合える隣の電気双極子が存在しないため誘電体表面に正・負電荷が現れる。この正・負電荷が分極電荷であり、自由に移動したり外部に取り出したりできない電荷である。
次ページから…
次ページでは、真電荷から電束が生じ、次のガウスの法則を満たす電束密度\(\boldsymbol D\)が電束から生じると定義する。
【前ページ】 【次ページ】